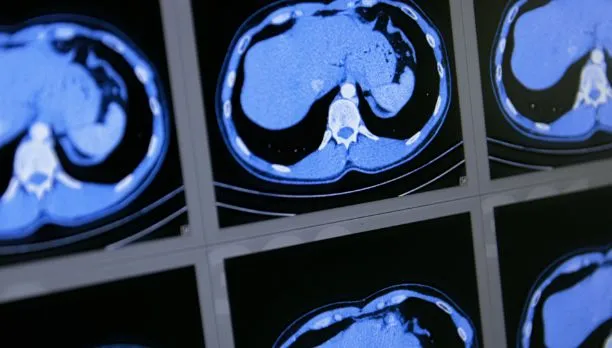監修:独立行政法人国立病院機構 久里浜医療センター 精神科医長
湯本洋介先生
アルコール健康障害に関連するガイドライン
AUD(アルコール使用症/アルコール使用障害)の早期発見と適切な介入は、健康の維持にとても重要です。そこで、アルコール健康障害に関連するガイドラインが策定され、検査やスクリーニングの方法が示されています。
健康診断および保健指導におけるアルコール健康障害への早期介入に関するガイドライン(厚生労働省 令和5年度障害者総合福祉推進事業、研究代表者 吉本尚)
アルコール健康障害の早期発見から治療、回復までの一連の切れ目のない取り組みを推進するためのガイドラインです。アルコール健康障害とはアルコールに関連する健康障害全てを指す用語です。特定健康診査(以下、特定健診)を例とした、AUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)を用いない減酒指導対象者のスクリーニングと保健指導のフローチャートの概要を以下に示します。
減酒指導対象者の抽出
特定健診の質問票で得られる飲酒頻度と飲酒量を元にして、飲酒によるリスクが高い者(図1)を抽出します。
(図1)
| (男性) | 1合未満 | 1〜2合未満 | 2〜3合未満 | 3〜5合未満 | 5合以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 生活習慣病のリスクを高める量を 飲酒している者 |
||||
| 週5〜6日 | |||||
| 週3~4日 | |||||
| 週1~2日 | 追加 | ||||
| 月1〜3日 | |||||
※この表は画面幅が不足した場合横スクロールで閲覧できます
| (女性) | 1合未満 | 1〜2合未満 | 2〜3合未満 | 3〜5合未満 | 5合以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 生活習慣病のリスクを高める量を 飲酒している者 |
||||
| 週5〜6日 | |||||
| 週3~4日 | |||||
| 週1~2日 | |||||
| 月1〜3日 | 追加 | ||||
※この表は画面幅が不足した場合横スクロールで閲覧できます
※標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度)p.110に記載の「生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者」に加えて、一時多量飲酒を含める。追加部分は一時多量飲酒(1回の飲酒機会で純アルコール摂取量60g以上)にあたる。
特定健診の項目より、保健指導判定値および受診勧奨値の該当者(図2)を抽出します。
(図2)
| 項目名 | 保健指導判定値 | 受診勧奨判定値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 収縮期血圧 | ≧130 | ≧140 | mmHg |
| 拡張期血圧 | ≧85 | ≧90 | mmHg |
| 空腹時中性脂肪 | ≧150 | ≧300 | mg/dl |
| 随時中性脂肪 | ≧175 | ≧300 | mg/dl |
| HDLコレステロール | <40 | ― | mg/dl |
| LDLコレステロール | ≧120 | ≧140 | mg/dl |
| Non-HDLコレステロール | ≧150 | ≧170 | mg/dl |
| 空腹時血糖 | ≧100 | ≧126 | mg/dl |
| HbA1c(NGSP) | ≧5.6 | ≧6.5 | % |
| 随時血糖 | ≧100 | ≧126 | mg/dl |
| AST(GOT) | ≧31 | ≧51 | U/L |
| ALT(GPT) | ≧31 | ≧51 | U/L |
| γ-GT(γ-GTP) | ≧51 | ≧101 | U/L |
※この表は画面幅が不足した場合横スクロールで閲覧できます
保健指導を行うフローチャート

初回面接
| STEP1 | アセスメント 問診票回答での飲酒習慣の確認および健診結果の説明 |
|---|---|
| STEP2 | 過剰飲酒による身体への影響および健康に対するリスク説明 |
| STEP3 | 飲酒習慣の振り返り
|
| STEP4 | 減酒に関わる目標設定 |
| STEP5 | 今後の支援スケジュール確認 |
継続的支援(1か月後、2か月後)
飲酒状況、目標達成状況を確認する。達成度に応じて賞賛し、必要に応じて目標を修正する。
実績評価(3か月後)
- 継続支援が必要な場合は支援期間を延長する。
- 受診が必要な場合は受診を勧める。
- AUDITを実施し、15点以上の場合にはアルコール依存症に対応が可能な医療機関へ繋げることが望ましい。
監修医による解説
厚生労働省による標準的な健診・保険指導プログラムでは、生活習慣病のリスクを高める飲酒(一日の平均純アルコール摂取量が男性40g、女性20g以上)に該当する場合はAUDITによる飲酒状況の評価を行い、その点数に応じて減酒支援・指導を行うことが望ましいとされています。しかしながら、厚生労働省 令和5年度 障害者総合福祉推進事業のなかで実施された健康経営優良企業に選定された会社を対象にした調査では、AUDITの実施率は10.1%、減酒支援・指導の実施率は1.2%に過ぎませんでした。健康診断などでの質問項目に新たな項目を追加するのも簡単ではありません。
そこで、本ガイドラインでは、AUDITの最初の2項目「あなたはアルコール含有飲料をどのくらいの頻度で飲みますか?」、「飲酒するときには通常どのくらいの量を飲みますか?」のみでのスクリーニングを提案しています。AUDITの最初の2問だけでも十分なスクリーニングが可能とされているからです。飲酒頻度、1回あたりの飲酒量であれば、既存の健診項目に入っているケースも多いでしょう。アルコール健康障害への早期介入の取り組みを促進するために、現実的で実行可能性の高い提案となっています。
2025年7月作成
参考
アルコール健康障害に係る地域医療連携等の効果検証および関係者連携会議の実態調査に関する研究(厚生労働省 令和5年度障害者総合福祉推進事業、研究代表者 吉本尚)(2025年7月閲覧)